― 特許の話より、先に語るべきこと ―
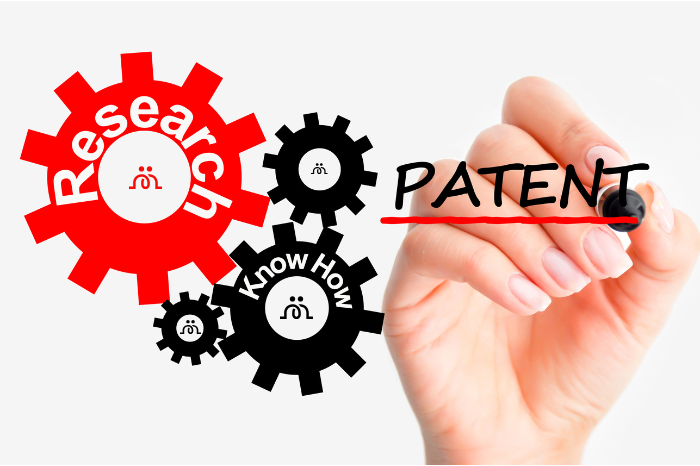
なぜか、響かない技術の話
「当社はこの技術で特許を取りました」
「他社にはない独自の構造なんです」
-技術に自信を持つ経営者ほど、こう語りがちです。
けれど、相手の反応は薄く、「へぇ、すごいですね」で終わってしまう。
このような経験、ありませんか?
実は、「特許がある」「独自性がある」という事実と、「価値が伝わる」ということは、まったくの別物です。
取引先も、金融機関も、投資家も、聞いているのは、その技術が
「何のためにあるのか」「どんな良い変化を生むのか」。
つまり、「機能」ではなく「意味」を知りたいのです。
「軽いです」では、価値は伝わらない
たとえば、ある製品に「他社より10%軽い」という特徴があったとします。
これは確かに技術的な強みかもしれません。しかし、それだけでは相手の心には残りません。
むしろ、
「この軽さで作業者の負担が減る」
「作業効率が上がり、現場の疲労感が軽くなる」-
そう語った方が、相手は自分ごととしてその技術の意味を受け取ってくれます。
特許は、技術そのものを守るための制度です。
けれど、それだけでは技術の価値は伝わりません。
その価値を相手に感じさせる役割を担うのが、ブランドです。
ブランドとは、技術によってもたらされる変化や意味を、相手に伝えるための「価値のかたち」なのです。
技術とは、未来をつくるための素材にすぎません。
その素材をどう活かせば、誰のどんな困りごとを減らせるのか。
それを経営者自身の言葉で語ったとき、ブランドの「芯」が生まれます。
技術の魅力は、「権利化した」だけでは伝わりません。
どんな価値を、誰に届けたいのか。
その問いに向き合ったとき、特許は「意味のある武器」として機能し始めるのです。
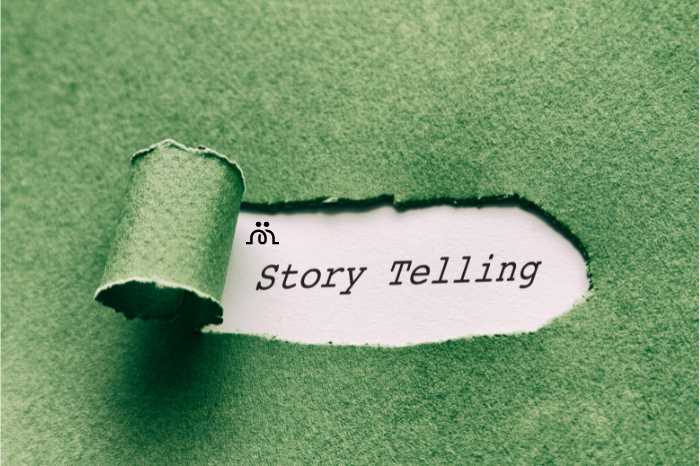
町工場の「伝え方」改革
ある町工場では、新しい加工技術で特許を取得し、「これを武器に営業強化を」と考えていました。
しかし、現実には反応が薄く、価格交渉ばかり。
特許があることを伝えても、「それが何の役に立つのか」が伝わっていなかったのです。
そこで、こう問いかけました。
「この技術によって、どんなお客様の困りごとが減るのでしょうか?」
「実際の現場では、どんな変化が起きているのですか?」
現場から出てきたのは、こんな声でした:
- 「独自の段差逃がし形状」で、従来は専用治具が必要だった製品が汎用治具で加工できるようになった。
⇒ その結果、段取り時間が1/3に短縮され、急ぎの注文にも即対応できるようになった - 加工の中心がブレにくい構造で、小ロットでもリピート品との寸法差がほぼ出ない
⇒ 顧客からは「いつ頼んでも品質が変わらない」と信頼されるようになった
こうした「現場のことば」で語るようになったことで、見積相談が増え、「一緒に開発したい」という声も届くようになったのです。

技術の話は「あとから」でいい
技術力がある会社ほど、「技術上の工夫」や「それが特許で守られていること」をアピールしがちです。
けれど、本当に伝えるべきなのは、
その技術で「誰のどんな困りごとを、どう解決するか」です。
つまり、語るべき順番はこうです:
先に「使う人の価値」を語る
その価値を支える「技術の仕組み」を紹介する
必要に応じて「特許で守っていること」を伝える
この順番を意識するだけで、相手の納得度も反応も大きく変わってきます。
「伝える順番」を整えること。それが、ブランドづくりの第一歩なのです。
特許の前に、語るべき「意味」がある
「その技術、なんのためにあるのか?」
この問いに答えられるとき、ブランドは動き出します。
特許は、価値を守るためのツールにすぎません。
その前に、経営者が語るべきなのは、その技術によって、誰にどんな未来を届けたいかという「意味」です。
小さな会社こそ、そこを言語化できたとき、ブランドは強くなり、技術も知財も「生きた武器」として活用できるようになります。