‐人ではなく仕組みを整える‐
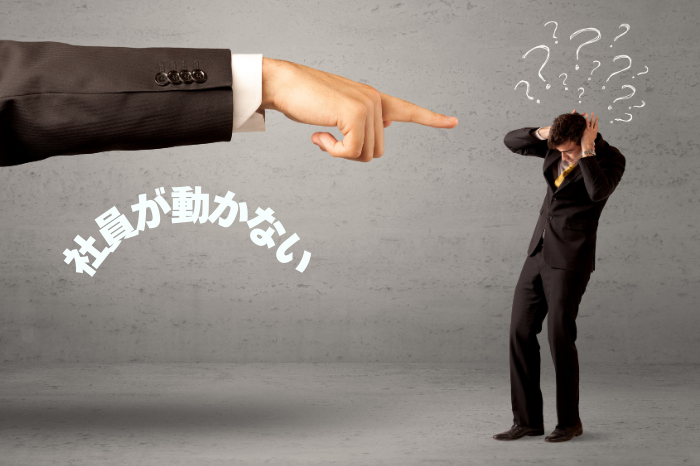
「社員が動かない」と感じるとき
「指示しても動かない」
「何度言っても改善されない」
「どうも社員にやる気がないように見える」
製造業の経営者の方から、こんな悩みをよく伺います。
ただ、実際に現場を見ていると、社員が「やりたくない」のではなく、どう動けばいいかが曖昧なまま放置されているケースが多いのです。
『やる気の問題』ではなく『仕組みの問題』
社員が「動かない」と感じるとき、その原因は社員自身にはなく、仕組みにあることがほとんどです。
- 判断基準があいまい
→「どこまでやればいいのか」が分からない - 情報が伝わらない
→指示が上司から末端まで届かず、途中で解釈が変わる - やっても評価されない
→改善しても成果が見えず、「やる意味」を感じられない
このように、社員が動かないのは、やる気ではなく行動を支える仕組みが整っていないからです。
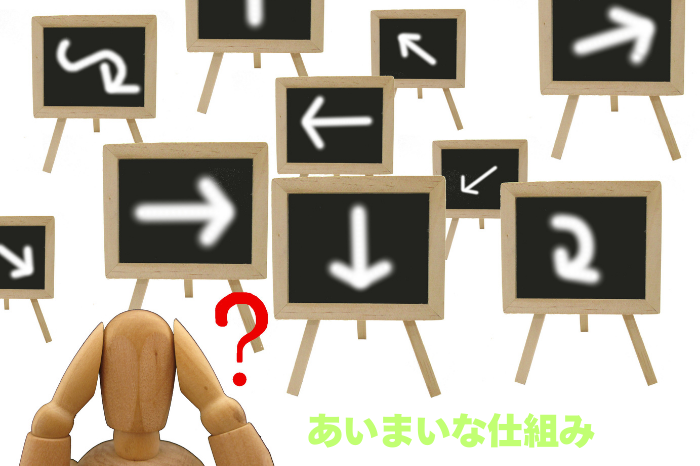
仕組みを整えたら動き出した現場
ある加工会社では、社長が「改善しろ」と言っても現場が動かず、苛立っていました。
ところが、ヒアリングしてみると-「改善した内容を共有する場もなく、評価もされない」状態だったのです。
そこで次の2つの仕組みを導入しました。
- 改善提案を月次会議で必ず共有する
- 小さな改善でも数値で効果を見える化し、表彰する
すると、現場から「これも改善になるのでは?」と自然に声が出始め、改善が連鎖。
社員が『やる気を出した』のではなく、仕組みが『やる気を引き出した』のです。
「仕組みを整える」とは何か?
「仕組みを整える」とは、難しい制度を入れることではありません。
次の3つを意識するだけで十分です。
- 判断基準を明確にする
(例:不良品が出たら「自分で調整」ではなく「班長に報告する」) - 情報の流れをつくる
(例:改善提案を必ず会議で取り上げる) - 行動が報われる仕掛けをつくる
(例:成果を数値で示し、承認・表彰する)

まとめ:「動かない社員」の正体は『曖昧な仕組み』
「社員が動かない」のは、『人のやる気』のせいではありません。
多くの場合は、『仕組みが曖昧』なことが原因です。
社員のやる気を疑う前に、
「動きやすい仕組みになっているか」を点検してみてください。
仕組みを整えれば、社員は自然と動き出します。
そして、その仕組みこそが、経営者がつくるべき『土台』なのです。